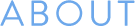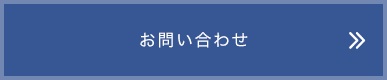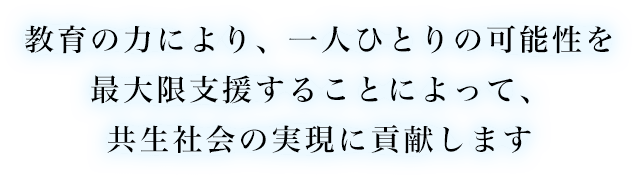
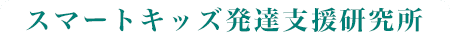
新着情報
- 2026.01.05
- スマートキッズ発達支援研究所便り「きらっと」69号を発行しました。
- 2025.12.01
- スマートキッズ発達支援研究所便り「きらっと」68号を発行しました。
- 2025.11.19
- スマートキッズ発達支援研究所便り「きらっと」67号を発行しました。
スマートキッズ発達支援研究所について

コンセプト
「スマートキッズ発達支援研究所」は、発達障害のある子どもたちに、健康で豊かな毎日を過ごしてほしいとの願いから、2019年に設立されました。
教育、医療、心理等の専門家が集まり、「児童発達支援ガイドライン」や「放課後等デイサービスガイドライン」を踏まえ、支援の向上につながるプログラム開発や効果的な活用などについて研究しています。また、健康な生活を送るための専門的な提案やテキストの作成、SDGsの推進、世界自閉症啓発デー及び発達障害者啓発週間の啓発活動に参加しています。
すべての子どもが、地域社会でいきいきと個性を生かして共生していくことができるよう研究と実践を積み上げてまいります。
SDGs(エス・ディー・ジーズ)への参画
本研究所は、国連の指針SDGs(Sustainable Development Goals持続可能な開発目標)に
賛同し、目標4「質の高い教育をみんなに」を推進します。
- 4.1 すべての子どもへの無償、公正で質の高い初等・中等教育
- 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。
- 4.2 すべての子どもへの質の高い乳幼児発達ケア・就学前教育
- 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。
- 4.4 雇用に必要な技能を備えた若者の増加
- 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。
- 4.5 教育における格差の撤廃
- 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。
- 4.6 すべての若者の読み・書き・計算能力の習得
- 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。
- 4.7 教育を通じた持続可能な開発の促進
- 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。
- 4.a すべての人を受け入れる学習環境
- 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。
- 4.b 開発途上国のための高等教育奨学金を拡大
- 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国およびその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。
- 4.c 開発途上国における質の高い教員の数を増加
- 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。
世界自閉症啓発デーの啓発参画
国連の定めた世界自閉症啓発デーの趣旨に賛同し、応援、参画いたします。

主席研究員
河村 久
(かわむら ひさし)
聖徳大学 教授
私は,現職に就く前には東京都の公立学校の教員,小学校長・幼稚園長として,主として障害のある子どもの教育に従事してきました。
この間,全国特別支援学級設置学校長協会会長(平成19年度),中央教育審議会専門委員(平成18年度~平成23年度)等を歴任しました。近年は,特別支援学校の学校運営のお手伝いをするとともに,通常の学級に在籍する発達障害のある子どもの教育に関する研究や現職の先生方への支援にかかわることが多くなってきました。
本研究所の活動に参画することによって,生きにくさを感じている子どもたちの発達支援と生活の充実のためにお役に立つことができたら,大変幸せなことと思っております。

猪狩 和子
(いかり かずこ)
耳鼻咽喉科北川医院 院長
医師として40数年間、生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで、ひとりひとりと向き合い、命と健康を守る仕事をしてきました。その中の20年間は保育園医として、小・中学校医として、日本の将来を担っていく子供たちの健康教育に携わっています。
順天堂大学、豊島区学校保健会と協力して、成長期の骨量不足から起こる骨粗鬆症を予防する取り組みである小中学校骨密度測定を10年前から行い、測定後、骨密度を上げるための食育、生活習慣について養護教諭と保健指導を実施し成果を上げています。
また、予防を中心としたがん教育は平成24年から実施し、禁煙教育、歯周病予防、性教育などの健康教育も行っています。「アクティブライフ研究校」の指定を受け独創的なアイデアを実施しました。
自らの合唱団活動としてかけがえのない命を考える「いのちの授業」―がん教育講演会とコンサート―など、文化を通じた癒しを与える教育活動、社会活動も続けています。
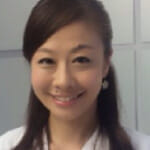
本田 由佳
(ほんだ ゆか)
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任講師
国立成育医療研究センター母性内科研究員、順天堂大学医学部小児科非常勤助教授
夢は、子どもたちの健康力を向上させて、日本を元気にすることです。これまで、小中学校の健康教育推進を医療面から支援し、学校の先生方と共に子どもたちの健康づくりに取り組むなど、教育と医療との連携を推進してきました。
<研究課題に関する実務活動>
厚生労働省:女性の健康の包括的支援政策研究事業 保健・医療・教育機関・産業等における女性の健康支援のための研究協力者
総務省:ICT健康モデル(予防)の確立に向けた退職時健康情報継続管理モデル棟に関する実証(子どものころから自分の体に関心をもつことの重要性)
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業:子どもの健康づくりのためのスポーツ医科学研究拠点の形成
文京区教育振興基本計画:子どもの健康と身体づくりの協力メンバーとして、子どもや親子の健康講座を実施

岡田 行雄
(おかだ ゆきお)
元帝京大学大学院教職研究科教授
東京都中学校の教員(理科)をへて、世田谷区教育委員会指導主事、東京都教育委員会、足立区教育委員会指導課長として、その時代の特色を反映した多様な教育課題の解決に関わってきました。例えば、生活指導に関わる問題、学校運営協議会の設立、学校選択制、生活科への対応、民間人校長の導入、学力向上対策などの制度設計から円滑な導入・運営などに関わりながら、教育委員会のスタッフや校長先生方と悪戦苦闘してきた日々を思い出します。その後、2校の中学校長として、小中一貫・連携校の設立における地域の方々との協働、また、全日本中学校長会総務部長として、都道府県校長会との連携、文科省や衆参両院の議員との協議・陳情などに関わり、自分の学区域を土台に全国的な視点で教育を考えさせていただく機会を持つことができました。
現在は、帝京大学教職大学院で若い教職志望の学生さんたちと過ごしておりますが、「山火事に立ち向かうハチドリの一滴」の大切さを胸に、小規模ながら私個人としてもNPO法人を仲間と設立し、子どもの貧困問題の解決に対する取り組みや子どもの社会貢献力を育む活動に取り組んでいます。
教員生活40数年にわたる自分の活動が本当に良かったのかという自問自答とともに、一方では、私と関わってくださった多くの方々へ感謝をしつつ、本研究所のこれからの活動に私の経験が何かのお役に立つのであれば幸いです。

荒巻 恵子
(あらまき けいこ)
帝京大学大学院教職研究科教授
子どもたちとの出会い、先生がたとの出会い、保護者との出会い。たくさんの出会いの中で、人が豊かになるのは、学校という場が、すべての人の学びの場であるためだと思います。インクルージョンが問われている多様性社会の中で、次代を生きる子どもたちの未来を、みんなで考えていくことは、現代を生きる私たちの使命です。先人たちと同様、いつの時代もよりよく生きるという「ウェルビーイング」を追究していくとき、教育の意義が見えてくると思います。皆さんとともに、一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願い致します。

小島 花観
(こじま はなみ)
臨床心理士、公認心理師
心理士として、医療現場、福祉の現場などに勤め、大人から子どもまで様々な方を対象に心の支援に携わってまいりました。現在は研究分野で心の健康について考える日々を送っています。今までの経験や知識を活かし、本研究所に参加することで、子どもたちや保護者様のお役に立つことができるのであれば、これ以上の幸いはございません。

福本 有紗
(ふくもと ありさ)
臨床心理士、公認心理師、保育士、幼稚園教諭
教育と心理を学び、現在はその知識や経験を活かして発達障害の子どもたちと毎日関わりながら過ごしています。一人ひとりの個性を大切にしながら、言葉で表現できない気持ちを心理の専門家からの目線でくみ取れるよう努力しています。
お子様だけでなく、日々関わる保護者様の支援や連携にも力を入れて取り組み、 子どもの持っている力を引き出しながら社会生活に大切なスキルを提供できるよう頑張ります。
村上 浩将
(むらかみ こうすけ)
臨床心理士、公認心理師、学校心理士
学校や児童発達支援、放課後等デイサービスにて、さまざまな個性がある子どもたちと直接かかわってきました。そして教育・心理の専門家として、一人ひとりの居場所をどのようにつくっていくのか、安心して成長できる場とはどんなものなのかを考え、実践してきました。 これからも「スモールステップ」でお子さまのもつスキルを伸ばし、いずれはお子さま自身が自分で居場所をつくっていけるように、保護者の皆さまと力を合わせた支援を提供していければと思っております。よろしくお願いいたします。

所長
中村 雅子
(なかむら まさこ)
スマートキッズ発達支援研究所は、教育と医療の連携を図り、日常生活に必要な基本動作を身に付け、集団への適応を図り、健康で生き生きと活躍するための優れた支援プログラムの開発と活用を目指します。多くの皆様にご活用いただければ幸いです。
私は、これまで、情緒障害教育研究会会長を5年間、設置校長を15年間務め、大学院で後進の育成に携わってきました。これまで、多くの保護者の皆様と出会い、率直なご意見を伺ってきました。その多くが、卒業後、就労し、社会の中で人とかかわり、生き生きと生きていくために、十分な教育ができているだろうかという不安でした。私たちは、このような問いと真摯に向かい合い、より有効な支援プログラムを開発し、その効果的な活用法を提言していきたいと考えています。また、学校(園)と放課後等デイサービス等の連携を図り、子どもたちの健康づくりやキャリア形成、遊びや余暇など生活づくりにつながるプログラム開発を進めます。研究所員の皆様は、教育、医療、心理の経験豊かな専門家です。皆様と共に、楽しく、生きやすく、働きやすい社会を創っていきたいと思います。
スマートキッズ発達支援研究所 規約
- 名称
- 本研究所は、「スマートキッズ発達支援研究所」という。
- 事務所・所在地
- 本研究所は、(株)スマートキッズ本社に帰属し、本社に事務局を置く。
千代田区神田小川町3-2-1 CIRCLES神田小川町3階
- 目的
- 本研究所は、スマートキッズの理念に基づき、
発達障害にかかわる教育研究及び福祉の推進を図ることをもって目的とする。
- 事業
- 1 発達障害にかかわる実践的教育研究にかかわること
2 実態調査にかかわること
3 研修にかかわること
4 教育、医療、福祉等、他機関との連携にかかわること
5 国内外を視野に渉外・情報交換にかかわること
6 啓発活動にかかわること
7 その他、目的を達成するために必要な事業
- 施行
- 2019年12月20日